「伝聞はもう一通りやった」でも、納得できていないあなたへ
定義も覚えたし、例外の条文も押さえた。
何度も過去問を解いてきたし、伝聞の出題には慣れているはずなのに、「本当に理解できているのか?」という不安がどこかに残る。
実際、こんな声が多くあります。
・伝聞か非伝聞か、要証事実と推認過程の整理が最後まで曖昧だった
・“真実性が問題となる”かどうかを形式的にしか判断できていない
・定義は出せるのに、答案での使い方になると自信がなくなる
・要証事実がそもそも何か、問題ごとにズレてる気がして怖い
構造の理解、要証事実の把握、条文との接続。どれかひとつでもズレていれば、答案全体があいまいになります。
一通りこなしたあとに残る、その不完全燃焼感。
それこそが、伝聞が“つかみどころのない論点”と言われる理由かもしれません。
伝聞の問題は、実は出題パターンがかなり絞られています。
・伝聞/非伝聞の判断
・例外適用の要否と処理の順番
・弾劾証拠との整理
といった伝聞処理の柱が、明確に整理できるようになります。
つまり、正しい型を覚えて実戦形式で反復すれば、伝聞は“得点差がつくテーマ”に変わるのです。
伝聞法則は出題パターンがほぼ出尽くしているからこそ、
実は「 旧司法試験の問題」が、演習素材として最適です。
・「過去問の知識があれば取れる」からこそ、本質的理解が問われる
・短い問題で、要証事実や推認過程の扱いを正確に訓練できる
司法試験・予備試験の過去問を終えて、「新しい問題に取り組みたい」「いい問題集がない」と感じていた方にこそ、ぜひ取り組んでいただきたいのが、旧司法試験の問題です。
「旧司の問題で回しておけばよかった」
30代・予備試験合格者インタビュー
でも、1問1問に時間をかけすぎる余裕はない。働きながらの勉強だったので、負担の大きい問題は後回しになってしまって……。
今振り返ると、旧司法試験の問題をもっと活用すべきだったなと思います。
問題文が短くて、それでいて伝聞や弾劾証拠みたいな“判断力が問われる論点”がきっちり出ている。
特に伝聞は、どこまでを要証事実として拾うのか、処理の型を練習するにはすごくいい素材だったと思います。
今だったら迷わず選びますね。時間をかけずに、ちゃんと身になる演習がしたいなら、あれ以上の素材はなかったなって。
理念・コンセプト
短時間で良問を回し、伝聞を仕上げる
この講座は、旧司法試験の良問10問を素材に、
伝聞法則の主要パターンを短時間で網羅的に整理するための講座です。
この講座の特徴
旧司の良問だけを使うから、短時間で質の高い演習が可能
無理にすべてを網羅しません。出尽くしたとされる伝聞分野の中で、今もなお有効なテーマ・視点を厳選。
「要証事実 → 証拠 → 論述」の視点を整理
推認過程と供述の意義を丁寧に解説し、非伝聞・例外・弾劾証拠の処理をスムーズに。
短時間で網羅的に仕上げたい方にも最適
忙しくて時間をかけられない方も、短時間で一気に仕上げられる構成に。
こんな方におすすめ
・伝聞の分野が苦手な方
・伝聞の分野を得意分野にしたい方
・伝聞の重要旧司過去問を短時間で習得したい方
・刑訴の勉強ににそこまで時間をかけられない方
・問題演習をしたいけど、いい教材がないとお悩みの方
講師インタビュー(QandA)
Q1. 「伝聞の出題パターンは絞られている」とのことですが、どのようなパターンを意識していますか?
Q2. 本講座では旧司法試験の問題を使うとのことですが、現在の試験対策として十分対応できますか?
Q3. 伝聞に苦手意識がある受験生に、どんな勉強方法を勧めますか?
受講条件

講座形式
定価
3,800円(税込)
カリキュラム
-
内藤慎太郎『短時間で伝聞完全攻略』 プランのカリキュラム
講義時間: 約1時間2分
配信状況: 全講義配信中内藤慎太郎『短時間で伝聞完全攻略』
第1回第2回第3回第4回第5回第6回第7回
この講座のおすすめコメント
この講座の評価
0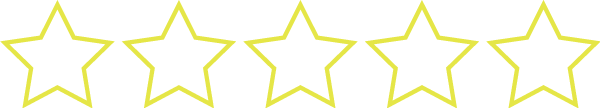
おすすめコメントはありません。









