刑法短答、時間が足りない……
「刑法短答は苦手だ」「試験時間がどうしても足りない」──そんな受験生は少なくありません。
パズル問題に時間を奪われ、判例や条文の細かい知識に翻弄され、学説の対立問題に混乱する……。
焦りや不安を抱えやすい科目だからこそ、効率的な学習法が必要です。
実は、合否を分けた“肢”だけ対策すれば点が伸びる!
【1万問を解き尽くした刑事系上位3%講師が教える】コスパよく得点力を伸ばす方法
復習しても同じ箇所でつまずく──それは人が「知らない知識」を自覚できないからです。
しかし、データを分析すると合否を分ける問題の肢は共通しています。
>>> そこだけをピックアップして学べば、効率よく得点力を伸ばせます!
本講座の特徴
特徴① データに裏付けられた「合否を分けた問題」を徹底演習
○やみくもに過去問を解くのではなく、合格者と不合格者を分けた問題だけをセレクト!
①正答率要件:正答率が以下の要件を満たすもの
㋐全体正答率が50%以上80%未満であること
㋑合格者(又は上位30%)と不合格者(又は下位30%)の正答率の差が15%以上あること
㋒不合格者(又は下位30%)の正答率が50%〜60%未満
※予備試験・司法試験共通問題の場合、一方のみで正答率要件を満たす場合には掲載をしています。
・不合格者正答率が50〜60%未満
②分野重複要件:同一知識の問題が複数ある場合、年度が新しいものを1つ選択
※以上に関わらず、講師が裁量により学習効果が高いものを選ぶ場合があります。
この基準でセレクトされた問題を演習することで、最短ルートで得点力を強化できます。
つまり、セレクトされた問題を解くことで、膨大な問題から合否を分けた肢だけを効率的に学習することができ、本講座を受講すれば、最後の2肢で悩まず、自信をもって確実に正答を選ぶことができるようになります。
特徴② 合格者の思考法を学び、短時間で正解に近づく
○正解にたどり着けなかった時の「見切り方」
・パズル(穴埋め)問題の攻略法
・時間配分と戦略の立て方
個別指導歴10年以上、短答刑事系上位2%合格の実績を持つ藤澤講師が、短答肢1万以上を検討してきた経験をもとに解説します。
特徴③ 基礎から考える習慣を身につけ、論文にも活かす
○「なぜその規定があるのか」を重視して丁寧に解説。
多くの受験生は「短答は短答、論文は論文」と分けて考えがちです。
しかし──刑法は違います。
刑法では、短答と論文で同じ判例が何度も問われることが少なくありません。
さらに、各論の構成要件を瞬発的に思い出す力は、そのまま論文答案の「書き出しの速さ」「検討の切れ味」に直結します。
つまり、刑法短答の学習は単なる“マークシート対策”ではなく、
論文試験を勝ち抜くための実戦的トレーニングでもあるのです。
短答を極めることが、論文での安定した得点力につながる──それが、刑法という科目の最大の特徴です。
・短答では、「初見問題に対応する力」
・論文では、「現場で答案を構成する力」
以上のように、短答・論文に通じる“基礎力”を養うことができます。
■使用教材:短答過去問パーフェクトとは?
司法試験・予備試験の短答対策において最も定番かつ信頼性の高い過去問集であり、多くの合格者が「この一冊で短答を突破した」と語る教材です。
〇講師紹介:藤澤 潤講師

・短答刑事系で全国上位3%の実績(H24年司法試験)
・短答肢1万以上を徹底検討
短答の重要性と効率的な攻略法を誰よりも理解している“短答のプロ講師”
講師メッセージ
刑法短答の学習は、論文試験での瞬発力にも必ずつながります。
本講座で、合否を分けた問題を効率よく押さえ、迷ったときに正しく選べる力を身につけてください。
刑法短答で時間に追われる不安を解消し、合否を分ける問題を確実に得点源に。
〇受講形式
・講座形式

・通常販売価格
19,800円(税込)
カリキュラム
-
藤澤潤『コスパ最強!短答過去問セレクト講義(刑法)』 プランのカリキュラム
- 講義時間: 約12時間33分
- 配信状況: 全講義配信中
藤澤潤『コスパ最強!短答過去問セレクト講義(刑法)』 講座数 100 12時間33分
-
第1回 司法試験 H23-205分
-
第2回 司法試験 R2-78分
-
第3回 司法試験 H28-178分
-
第4回 司法試験 H29-19分
-
第5回 司法試験 H22-27分
-
第6回 司法試験 H21-26分
-
第7回 司法試験 H27-36分
-
第8回 司法試験 H22-67分
-
第9回 司法試験 H26-13/予備試験 H26-710分
-
第10回 司法試験 H27-99分
-
第11回 予備試験 H28-1111分
-
第12回 司法試験 H29-33分
-
第13回 司法試験 H30-37分
-
第14回 司法試験 H25-135分
-
第15回 司法試験 H22-412分
-
第16回 司法試験 H24-26分
-
第17回 司法試験 H27-78分
-
第18回 司法試験 R2-1715分
-
第19回 司法試験 R1-97分
-
第20回 司法試験 H22-146分
-
第21回 予備試験 H27-117分
-
第22回 司法試験 H30-11/予備試験 H30-116分
-
第23回 司法試験 R2-9/予備試験 R2-911分
-
第24回 司法試験 H20-114分
-
第25回 司法試験 H29-176分
-
第26回 司法試験 H27-5/予備試験 H27-111分
-
第27回 司法試験 R1-13/予備試験 R1-119分
-
第28回 司法試験 R2-117分
-
第29回 司法試験 H20-158分
-
第30回 司法試験 H27-138分
-
第31回 司法試験 H30-158分
-
第32回 司法試験 H22-54分
-
第33回 司法試験 H24-2/予備試験 H24-44分
-
第34回 司法試験 H22-126分
-
第35回 司法試験 R3-15/予備試験 R3-714分
-
第36回 司法試験 H23-611分
-
第37回 予備試験 H27-173分
-
第38回 司法試験 H24-208分
-
第39回 司法試験 H29-95分
-
第40回 司法試験 H25-96分
-
第41回 司法試験 H30-96分
-
第42回 司法試験 R2-15/予備試験 R2-76分
-
第43回 司法試験 R3-77分
-
第44回 司法試験 H20-147分
-
第45回 司法試験 H20-127分
-
第46回 予備試験 H29-69分
-
第47回 司法試験 H24-4/予備試験 H24-57分
-
第48回 司法試験 H28-6/予備試験 H28-47分
-
第49回 司法試験 H26-126分
-
第50回 司法試験 R3-814分
-
第51回 予備試験 H29-106分
-
第52回 予備試験 H24-18分
-
第53回 司法試験 H25-46分
-
第54回 司法試験 H30-8/予備試験 H30-511分
-
第55回 司法試験 H22-189分
-
第56回 予備試験 H27-106分
-
第57回 司法試験 R1-29分
-
第58回 司法試験 R3-18/予備試験 R3-28分
-
第59回 司法試験 H26-810分
-
第60回 司法試験 R1-1611分
-
第61回 司法試験 R2-188分
-
第62回 司法試験 H20-188分
-
第63回 司法試験 H28-211分
-
第64回 司法試験 H27-127分
-
第65回 予備試験 H24-39分
-
第66回 予備試験 H28-210分
-
第67回 司法試験 R2-145分
-
第68回 司法試験 R3-168分
-
第69回 司法試験 H20-89分
-
第70回 司法試験 H21-97分
-
第71回 司法試験 H28-4/予備試験 H28-66分
-
第72回 司法試験 H30-4/予備試験 H30-126分
-
第73回 司法試験 H25-169分
-
第74回 司法試験 H27-18/予備試験 H27-47分
-
第75回 司法試験 H21-715分
-
第76回 司法試験 H28-184分
-
第77回 司法試験 H30-146分
-
第78回 司法試験 H23-11/予備試験 H23-25分
-
第79回 司法試験 R1-183分
-
第80回 司法試験 H21-16分
-
第81回 司法試験 H21-176分
-
第82回 司法試験 H22-18分
-
第83回 司法試験 H22-203分
-
第84回 司法試験 H25-20 /予備試験 H25-1213分
-
第85回 予備試験 H27-138分
-
第86回 司法試験 H29-20/予備試験 H29-136分
-
第87回 司法試験 H30-2/予備試験 H30-79分
-
第88回 司法試験 R1-206分
-
第89回 司法試験 R2-104分
-
第90回 司法試験 R2-205分
-
第91回 予備試験 R2-59分
-
第92回 司法試験 R5-15分
-
第93回 予備試験 R6-68分
-
第94回 司法試験 R6-168分
-
第95回 司法試験 R5-169分
-
第96回 司法試験 R4-117分
-
第97回 司法試験 R6-66分
-
第98回 予備試験 R4-46分
-
第99回 司法試験 R6-107分
-
第100回 司法試験 R4-610分
講義を閉じる
この講座のおすすめコメント
この講座の評価
0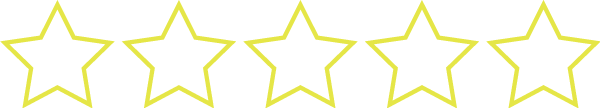
おすすめコメントはありません。






 [司法試験]H30-3
[司法試験]H30-3
 [司法試験]H22-12
[司法試験]H22-12
 [予備試験]R6-6
[予備試験]R6-6








