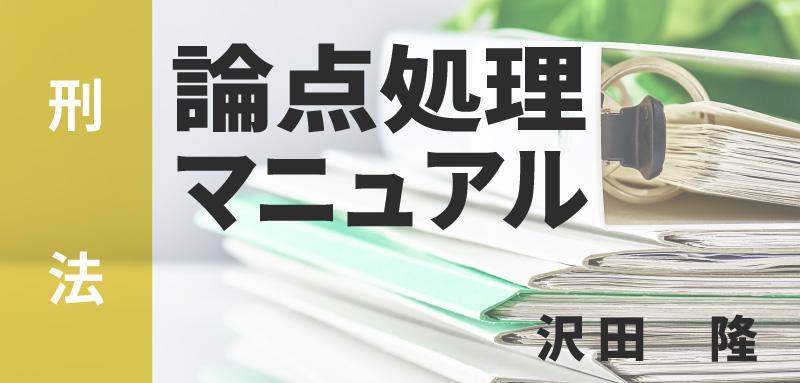【1万問を解き尽くした刑事系上位3%講師が教える】コスパよく短答で勝つ“思考法”が身につく!
刑事訴訟法は、“理解と整理”で必ず伸びる科目。しかも合否を分けた問題は繰り返し出る。
だからこそ、“出るところ”に絞ったデータ学習で効率的に点数に繋げる!
刑事訴訟法の短答が、どうしても点が伸びない…
・「条文は読んでいるのに、どこが問われるのか分からない」
・「判例が多すぎて整理できない」
・「細かすぎて、どこまで覚えればいいのか分からない」
──刑事訴訟法の短答には、こうした悩みを抱える受験生が非常に多くいます。
捜査・証拠・公判など手続の流れが複雑で、条文と判例の関係も入り組んでいるため、努力しても成果が見えづらいのが刑訴の特徴です。
しかし、点が伸びないのは「努力不足」ではありません。整理の仕方と考え方を知らないだけなのです。
刑事訴訟法の短答問題は「繰り返し出題される!?」──だから“基本”で勝てる!
実は、刑事訴訟法の短答試験問題では、同一制度・同一論点の類似問題が何度も出題されます
特に、合否を分けた問題ほど繰り返し出題される傾向が強く、一度“構造”として理解すれば、次年度以降も確実に得点できます。
つまり刑事訴訟法は、「運で決まる試験」ではなく、“基本を理解していれば再現できる試験”なのです。
本講座では、講師が1万肢以上を分析して導いた「出る条文・出る判例・繰り返し問われる論点」を体系化!
難しい学説や例外にとらわれず、「なぜこの制度があるのか」という本質に立ち返りながら、
条文・制度・趣旨を結びつける“考える力”を育てます。
結果として、膨大な知識を“使える知識”に変え、どんなに複雑な問題でも基本に戻って解ける“安定した思考力”が身につくのです。
本講座の特徴
特徴① “出るところ”に絞ったデータ学習でコスパよくスコアアップ!
○やみくもに過去問を解くのではなく、合格者と不合格者を分けた問題だけをセレクト!
①正答率要件:正答率が以下の要件を満たすもの
㋐全体正答率が50%以上80%未満であること
㋑合格者(又は上位30%)と不合格者(又は下位30%)の正答率の差が15%以上あること
㋒不合格者(又は下位30%)の正答率が50%〜60%未満
※予備試験・司法試験共通問題の場合、一方のみで正答率要件を満たす場合には掲載をしています。
・不合格者正答率が50〜60%未満
②分野重複要件:同一知識の問題が複数ある場合、年度が新しいものを1つ選択
※以上に関わらず、講師が裁量により学習効果が高いものを選ぶ場合があります。
この基準でセレクトされた問題を演習することで、最短ルートで得点力を強化できます。
つまり、セレクトされた問題を解くことで、膨大な問題から合否を分けた肢だけを効率的に学習することができ、本講座を受講すれば、最後の2肢で悩まず、自信をもって確実に正答を選ぶことができるようになります。
特徴② “基本から考える力”を鍛え、初見問題でもブレない!
本講座は、難解な学説や例外よりも「なぜこの制度が存在するのか」という原点から解説します。
条文や制度の根拠を理解することで、知識がぶれず、初見の問題にも自力で対応可能。
どんなに複雑な問題でも、基本に戻って解ける“安定した思考力”を育てます。理解を積み重ねるからこそ、再現性のある得点が可能になります。
特徴③ 条文・判例・趣旨を“線でつなぐ”理解で、得点が伸びる!
刑訴の短答で最も多いミスは、条文と判例、そして趣旨をバラバラに覚えていること。
本講座では、講師が1万肢以上を分析して導いた「出る条文・出る判例の構造」をもとに、各判例がどの条文を補い、どんな理由でその結論に至ったのかを明快に整理します。
さらに、単なる知識の暗記ではなく、「なぜこの制度があるのか」「なぜこのように定められているのか」という趣旨から解説。
点で覚えた知識が線でつながり、理解の深さがそのまま応用問題や複合問題への対応力に繋げられるようになります。
時間配分と見切り判断まで、刑事系上位3%合格者の思考法を再現!
刑訴短答は、文章量が多く時間との戦い。
講師が短答刑事系で全国上位3%の実績を出した経験をもとに、限られた時間で正解にたどり着くための思考の順番・見切りのコツ・読むべきポイントを徹底解説。
試験そのものを想定した“リアルな解答プロセス”で、現場対応力が身につきます!
〇講師紹介:藤澤 潤講師

・短答刑事系で全国上位3%の実績(H24年司法試験)
・短答肢1万以上を徹底検討
短答の重要性と効率的な攻略法を誰よりも理解している“短答のプロ講師”
講師メッセージ
〇受講形式
・講座形式

・通常販売価格
19,800円(税込)
※【R4-6年ご購入者の方限定】対象講座の受講ページの「オプションプラン」にて、10,800円(税込)でアップグレードいただけます。
カリキュラム
-
藤澤潤『コスパ最強!短答過去問セレクト講義(刑事訴訟法)【6年度版】』 プランのカリキュラム
- 講義時間: 約11時間51分
- 配信状況: 全講義配信中
藤澤潤『コスパ最強!短答過去問セレクト講義(刑事訴訟法)【6年度版】』 講座数 82 11時間51分
-
第1回 司法試験 H25-2312分
-
第2回 司法試験 H25-2511分
-
第3回 司法試験 H26-219分
-
第4回 司法試験 H25-21/予備試験 H25-1415分
-
第5回 予備試験 H25-158分
-
第6回 予備試験 R2-1413分
-
第7回 予備試験 R3-147分
-
第8回 予備試験 R2-1511分
-
第9回 予備試験 H27-1512分
-
第10回 予備試験 H23-158分
-
第11回 司法試験 H24-21-エ12分
-
第12回 司法試験 H20-268分
-
第13回 予備試験 H30-163分
-
第14回 司法試験 H21-2410分
-
第15回 予備試験 H24-144分
-
第16回 予備試験 H27-166分
-
第17回 予備試験 H30-227分
-
第18回 司法試験 H26-38/予備試験 H26-249分
-
第19回 予備試験 H27-255分
-
第20回 予備試験 H29-203分
-
第21回 予備試験 H24-1510分
-
第22回 予備試験 H28-1610分
-
第23回 司法試験 H24-345分
-
第24回 予備試験 H29-178分
-
第25回 予備試験 R2-187分
-
第26回 司法試験 H23-2612分
-
第27回 司法試験 H20-2912分
-
第28回 司法試験 H23-3715分
-
第29回 司法試験 H22-259分
-
第30回 司法試験 H22-397分
-
第31回 司法試験 H25-2716分
-
第32回 予備試験 H28-1717分
-
第33回 司法試験 H26-316分
-
第34回 司法試験 H21-2710分
-
第35回 司法試験 H21-299分
-
第36回 司法試験 H24-41/予備試験 H24-259分
-
第37回 司法試験 H26-399分
-
第38回 司法試験 H21-309分
-
第39回 予備試験 H28-196分
-
第40回 司法試験 H22-375分
-
第41回 予備試験 H24-165分
-
第42回 予備試験 R1-196分
-
第43回 司法試験 H21-335分
-
第44回 司法試験 H23-27/予備試験 H23-186分
-
第45回 予備試験 H28-256分
-
第46回 予備試験 R1-2014分
-
第47回 司法試験 H26-3216分
-
第48回 予備試験 H30-247分
-
第49回 司法試験 H20-348分
-
第50回 予備試験 H25-216分
-
第51回 司法試験 H23-319分
-
第52回 予備試験 H30-2310分
-
第53回 予備試験 H29-218分
-
第54回 司法試験 H22-3110分
-
第55回 司法試験 H20-395分
-
第56回 予備試験 R1-22-ア10分
-
第57回 予備試験 R3-2313分
-
第58回 予備試験 H23-238分
-
第59回 司法試験 H26-349分
-
第60回 司法試験 H26-266分
-
第61回 予備試験 H30-2513分
-
第62回 予備試験 R3-228分
-
第63回 司法試験 H22-3613分
-
第64回 司法試験 H24-3712分
-
第65回 予備試験 R2-269分
-
第66回 予備試験 H27-218分
-
第67回 司法試験 H21-3913分
-
第68回 司法試験 H25-39/予備試験 H25-266分
-
第69回 司法試験 H24-388分
-
第70回 予備試験 R1-264分
-
第71回 予備試験 R3-268分
-
第72回 司法試験 H24-39/予備試験 H24-246分
-
第73回 司法試験 H22-3812分
-
第74回 予備試験 R6-165分
-
第75回 予備試験 R6-198分
-
第76回 予備試験 R4-207分
-
第77回 予備試験 R4-219分
-
第78回 予備試験 R5-207分
-
第79回 予備試験 R5-226分
-
第80回 予備試験 R6-247分
-
第81回 予備試験 R4-265分
-
第82回 予備試験 R5-266分
講義を閉じる
この講座のおすすめコメント
この講座の評価
0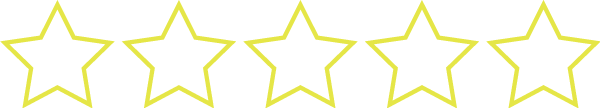
おすすめコメントはありません。
この講座を買った人はこの講座も買いました
講座に悩んだら

決して軽視できない司法試験短答式試験【司法試験の道しるべ②】
令和7年司法試験の結果を基に、短答式試験の得点が最終合否に与える影響を分析。短答の1点が合否を左右するため、来年の合格を目指す受験生には短答対策強化の必要性があります。






 [司法試験]H25-23
[司法試験]H25-23
 [予備試験]R6-19
[予備試験]R6-19