
SALE あと11日刑法C評価以下のあなたが絶対に解くべき旧司法試験・予備試験10選
岡野伸聡『刑法C評価以下のあなたが絶対に解くべき旧司法試験・予備試験10選』
体験動画・資料
共謀を認定した後にまた故意を書いていませんか?
こんな勘違いしていませんか?
・共謀を認定した後に再び故意を検討している
・共謀の射程・共犯の錯誤・共犯関係の離脱を混在させている
・過剰防衛の行為の一体性の検討を正当防衛の要件の中で検討している
・「窃取」を認定した後で死者の占有を検討している
近年の刑法予備論文試験は、あてはめ重視で書き負けない答案が評価されていると考えられがちです。たしかに、あてはめでどう評価するかが点数に大きな影響があるのは間違いありません。
しかし、刑法の点数が伸びないのはあてはめで他の受験生に負けているからなのでしょうか?
答案構成段階の二重認定で試験委員に「本当に理解しているのか?」と怪しまれているからではないでしょうか?
試験委員に「本当に理解しているのか?」とノイズを入れさせることは回避すべき
二重認定とは、一度構成要件の有無を認定しているにもかかわらず、別の場所で本来その構成要件内で検討すべきものを再度認定していることを指します。
よくある誤りが共謀の認定と故意の関係です。
二重認定をしてしまうと、いかにあてはめが素晴らしかろうが、試験委員に刑法理論を理解していないのでは?というノイズを入れさせてしまいます。
つまり、あてはめの前段階答案構成段階、もっと言えば各刑法論点の「論じる順番」「論じる場所」で損をしている可能性があるのです。
理念・コンセプト
刑法は得意意識のある受験生が多い科目である反面、少しの理解不足で評価を大きく落としてしまうリスクがある科目でもあります。この講座の狙いは、採点者の「本当に理解しているのか?」というノイズを排除できる答案を作成する能力を鍛え、少しの理解不足で評価を落とすことを防ぐことにあります。
担当の岡野伸聡講師は約4年間答案指導に携わられていた先生で、「知識はあるのだろうが理解していない」と思われる答案を多く添削指導してきた経歴の持ち主です。
刑法は他の科目に比べて論じるべき順番や場所がわかりやすい科目のはずであるにもかかわらず、意外に論ずべき順番・場所を意識できず損をしている受験生が多いことに気付き、本講座を製作しました。
特に独学で学習をしていると知識体系を誤解して理解してしまう傾向があるため、本講座で論ずべき順番・場所を理解できれば、あなたの知識体系や刑法の理解度を深くすることが可能です。
この講座の特徴
①論じる順番や場所の意識付けをしやすい10問の問題を選定
本講座は「論じる順番」「論ずべき場所」を整理整頓する学習をするのに効果的な10問を岡野講師が選定しています。
旧司法試験は、平成22年まで実施されていた難易度が高い問題ではありますが、実は刑法では今の受験生の論文知識でも十分に合格レベルに達する問題が出題されています。むしろそういう問題は、「論じる順番」「論ずべき場所」で合否が分かれている問題であるといえ、現在の論文試験でも大いに役立たせることが可能です。
②問題→論点の図解→答案構成例・答案例の順番で論じる順番と場所を特定
本講座では問題文から想起されるべき論点を一覧で図解した上で各論点の基本事項を解説し、その上で答案構成例(場合によっては答案例)で論じる順番と場所を特定します。
この講座を受ければ、論点や論証をパーツパーツで覚えていた部分が、どの構成要件内で論ずればいいのか、はたまた論じてはいけないのかを理解することが可能です。
たとえば、過剰防衛の行為の一体性を正当防衛の構成要件内で扱ってしまうといった、意外に勘違いして書いてしまうポイントなどを理解することが可能です。
③類似論点の位置づけを明確化
本講座では特に共犯関係で誤解しがちな類似論点についても意識的に明確にしています。
たとえば、共謀の射程・共犯の錯誤・共犯関係の離脱など、似ているようで論ずべき場所が異なる部分について図解内で解説をしています。
④刑法において超重要な「行為の特定」にも言及
刑法の答案構成において一番最初にやるべきもので、その後の答案構成に最も影響がある「行為の特定」「行為の一体性」についても言及します。
行為の特定を誤ったり、明確にせずに答案構成してしまうと、後々答案がごちゃごちゃになったりしてしまいます。
本講座では「行為の特定」「行為の一体性」を常に意識させることで、筋だった答案構成ができるように工夫をしています。
講座内容

・問題→論点の図解→答案構成例・答案例の順番で論じる順番と場所を特定

・応用刑法や刑法の悩みどころについても言及
取り扱い問題
①旧司法試験 平成16年1問
②旧司法試験 15年1問
③旧司法試験 平成14年1問
④予備試験 平成25年
⑤旧司法試験 平成21年1問
⑥旧司法試験 平成12年1問
⑦旧司法試験 平成17年1問
⑧旧司法試験 平成18年2問
⑨旧司法試験 平成21年2問
⑩予備試験 平成27年
受講条件

講座形式
定価
15,000円(税込)
カリキュラム
-
岡野伸聡『刑法C評価以下のあなたが絶対に解くべき旧司法試験・予備試験10選』 プランのカリキュラム
講義時間: 約6時間48分
配信状況: 全講義配信中岡野伸聡『刑法C評価以下のあなたが絶対に解くべき旧司法試験・予備試験10選』
第1回第2回第3回第4回第5回第6回第7回第8回第9回第10回第11回第12回第13回第14回第15回第16回第17回第18回第19回第20回第21回第22回第23回第24回第25回第26回第27回第28回第29回
この講座のおすすめコメント
この講座の評価
0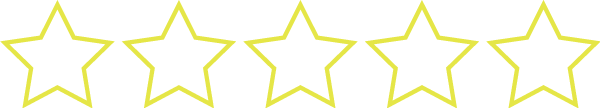
おすすめコメントはありません。









