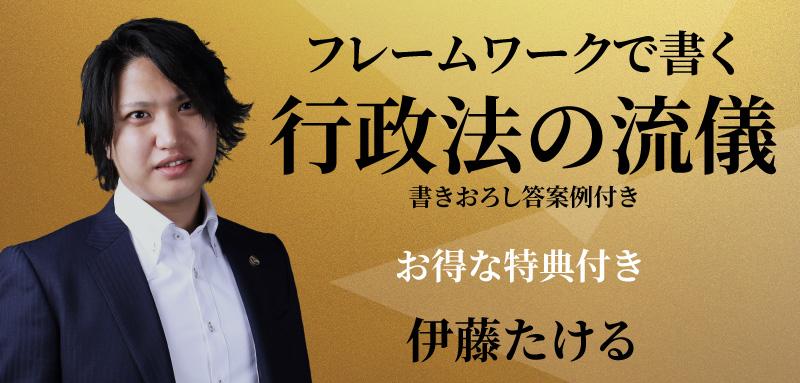伊藤たけるが弁護団として最高裁弁論した「いのちのとりで裁判」とは?最高裁逆転勝訴!

「いのちのとりで裁判」とは?
「いのちのとりで裁判」は、2013年に行われた生活保護基準の大幅な引き下げが、憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害するか否かを問う、かつてない規模の訴訟です。貧困の現場から声が上がり、全国31の裁判にまで広がったこの訴訟は、社会保障制度の根幹と、憲法によって保障された生存権のあり方に正面から挑むものでした。
そして2025年6月27日、ついに最高裁が国の引き下げ措置を「違法」とする初の統一判断を示しました。
裁判の背景と経緯
この訴訟の発端は、2013年。当時の安倍政権下で、厚生労働省は「デフレ調整」などを理由に、生活保護基準の最大約10%引き下げを決定。これにより、3年間で約670億円もの保護費が削減されました。
同時期、お笑いタレントの母親の生活保護受給がメディアでバッシングされるなど、「生活保護たたき」が社会に広がっていました。その風潮に強い危機感を抱いた弁護士らは、同年7月に「これは生存権を侵害する違憲の施策だ」として、生活保護受給者に不服申し立てと提訴を呼びかけました。
目標1万人の呼びかけは、わずか2カ月で達成。引き下げによって生活に打撃を受けた受給者たちの怒りと不安が、各地で裁判として形になっていきました。
主な争点
「いのちのとりで裁判」では、生活保護基準の引き下げが争点となりました。主な争点として以下の3つが挙げられます。
1.国の減額措置(生活保護の引き下げ)が憲法第25条に違反していないか。
憲法25条と生活保護法の違憲性
2.専門家の意見の軽視
厚労省が生活保護基準部会の意見を軽視し、独自の判断で基準を決めたのではないか
3.「デフレ調整」の妥当性
引き下げの根拠とされた物価下落の実態や手法が適切だったのか
裁判所の判断の分裂
この裁判は、全国29の裁判所に31件の事件が係属しており、それぞれの判断は分かれていました。たとえば、高等裁判所レベルでも、原告側勝訴が7件、敗訴が5件となっていたのです。
今回、最高裁判所で審理されることとなったのは、最も早く判断された大阪訴訟の大阪高裁判決(原告側敗訴)と、愛知訴訟の名古屋高裁判決(保護の違法と国家賠償請求まで認めた原告側完全勝訴)の2つでした。
高等裁判所の判断が分かれる中、最高裁判所の判断が注目されていました。
最高裁の歴史的判断(2025年6月27日)
そして、2025年6月27日、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、生活保護基準引き下げを「生活保護法に違反し違法」と認定しました。国が基準引き下げの根拠とした「デフレ調整」は、専門的知見と整合せず、判断過程に過誤・欠落があったとされました。
これは、生活保護の基準そのものが最高裁で「違法」と判断された初の事例となります。
この判決によって、すでに審理中の地方裁判所の訴訟にも波及し、国は減額分の補填や制度見直しを迫られる可能性が高くなりました。
なぜ、この判決が歴史的勝訴といわれているかというと、これまでの最高裁は、社会保障に関する分野では、国会や厚生労働大臣に広い裁量を認めており、ほとんど違法になることがなかったからです。
朝日訴訟
第一審は、保護基準自体を違法と判断する画期的な判決を下しましたが、最高裁は、厚生大臣(当時)に広範な裁量権を認める「朝日訴訟基準」を定立しました。
この基準は、保護基準の設定は「厚生大臣の合目的的な裁量に委されており」直ちに違法とはならないが、「現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合、または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となる」としました。
こうした基準では、たとえば、生活保護費を月額3000円にするなど、よほど低いものとしない限り、違法と判断することはできません。
堀木訴訟
ところが、最高裁は、憲法25条の規定を具体的に立法措置として講じるかは「立法府の広い裁量にゆだねられており」、「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合」でなければ、裁判所が審査判断するのに適さないという堀木訴訟基準を適用しました。
この基準もやはり「よほどのことがない限り、憲法25条に違反しない」というものなのですが、以降の憲法25条違反判断枠組みのリーディングケースとして多くの判例で引用されました。
生活保護基準をめぐる歴史的勝訴!
このように、これまでの最高裁の流れからすると、生活保護基準の改定が違法とされることはないであろうと考えられていたのです。
今回の最高裁の判決は、こうした過去の緩やかな基準を適用せず、厚生労働大臣の判断について、専門的な知見と整合するか、統計等と合理的な関連性があるか、つまり、専門的な判断をきちっとしたのかを審査したのです。
ところが、今回の保護基準の改定は、専門家が「ダメ」といっていた、物価をそのまま反映したものであったことから、違法と判断されたのです。
社会保障の分野=広い裁量という、これまでの前例が覆り、自民党の目玉政策であった生活保護基準の引下げを、最高裁が毅然と違法と判断したことから、歴史的な勝訴といわれているのです。
憲法25条の生存権は、平成22年新司法試験、令和5年司法試験でも出題されています。この判決を機に、復習をしてみましょう!
最高裁の弁論ってどんな感じ?こちらもご覧ください!
関連講座
役に立った:0